茨城大学地球・地域環境共創機構(GLEC)は、令和6年12月12日(木)に水戸キャンパスにおいて「茨城大学地球・地域環境共創機構5周年記念シンポジウム」を開催しました。本シンポジウムは、2020年の設立から5周年を迎えたGLECのこれまでの活動を広く紹介するとともに、茨城大学が目指す「総合気候変動科学」構想を紹介し、その共創について議論しました。
学長挨拶では、GLECの前身の一つである地球変動適応科学研究機関(ICAS:2006年~2019年)設立からの歴史の一つとして、「サステイナビリティ学入門」という授業について紹介されました。太田学長は、「2008年当時と2024年の授業内容を比較すると、将来世代を含めた“人類”よりも今を生きる人間(人権)の問題が深刻化し、今を考える必要性が出てきている。その中でどう「総合気候変動科学」を生かしていくか考えていきたい。」と述べました。
また、GLECの部門活動報告について、「ビジネスの観点が欠けている。経済・社会・環境というカテゴリーで考えたときに、社会が平等でなければ経済は発展しないし、気候変動による自然災害が増えると経済は発展しない。適応策、緩和策を追求していく中で、もう一つビジネスにつながることを展開していくことが必要。」と訴えました。
(学長挨拶の様子)
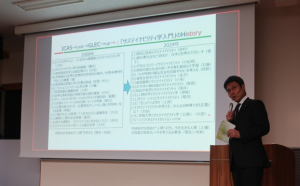
引き続き、戸嶋機構長からGLECの概要と本学が目指す「総合気候変動科学」について紹介をしました。
研究面では、GLECの4つの各部門(気候変動対応部門/流域圏環境部門/農業・生態系環境適応部門/人間・社会経済部門)からこれまでの研究成果と今後の展望について発表しました。
教育面では、サステイナビリティ学関連の教育に関する活動と水圏環境フィールドステーションの教育関係共同利用拠点(文部科学省指定)の活動について報告をしました。
パネルディスカッションでは、『「総合気候変動科学」の共創に向けて』をテーマに、亀山康子氏(東京大学)、古米弘明氏(中央大学)、羽井佐幸宏氏(環境省)をお招きし、戸嶋浩明機構長及び田村誠副機構長と議論をしました。
亀山氏からは、茨城大学の強みは適応策を担当するGLECにあり、特に農業・生態系環境適応部門のメタンと窒素を減らす技術開発と人間・社会経済部門の人々の認識や行動変容に関する研究にエールをいただきました。
古米氏からは、「総合気候変動科学」のどこに軸に置くのか、そしてその成果を明確に示すことが重要だと助言をいただきました。
羽井佐氏からは、科学的な成果が法に基づいて政策に反映される仕組みの重要性について説明の上、アカデミアに対し、エビデンスとなる研究成果への期待が寄せられました。
(パネルディスカッションの様子)

質疑応答では、茨城大学に対して、気候変動に関する学生や一般市民への教育などについて要望をいただきました。
閉会の挨拶では、金野理事からGLECへの「総合気候変動科学」の中心的な役割への期待が述べられ、教員だけでなく学生にも参加してもらって、「総合気候変動科学」を全学で進めていきたいとの意気込みが述べられました。
(閉会挨拶の様子)

